[ 国内特集① ]
しっとりとお月見、雅やかに神楽、
そして古式ゆかしい秋祭り
風流な日本の秋を心に刻む
企画=後藤秀幸/伊藤麻美子/金子美佐子
文=井上智之
燃えたぎるような夏から、“愁”を秘めた秋へ。めっきりと日暮れが早くなり、はらはらと木の葉が舞う季節の移ろいは、切なくも深い情感へと私たちを誘います。ご案内するのは、そんな日本の秋に行われる祭事を慈しむ旅。平安の世に迷い込んだかのような観月のひと時、神々の国・出雲での厳かな神楽鑑賞、そして飛騨高山・大津・京都で典雅な秋祭りをお楽しみいただける6つのコースをご用意しました。
紫式部も心奪われた名月を
貸切船と石山寺の境内から
紫式部が物語の構想を練った石山寺で優雅な「秋月祭」を
“今宵は十五夜なりけりと思し出でて、殿上の御遊び恋しく―”青年貴族が都から遠く離れた須磨で月を眺め、かつての暮らしを偲ぶこの1節(第十二帖『須磨』)こそは、紫式部が『源氏物語』の構想を練るべく参籠していた滋賀県・石山寺の名月からインスピレーションを得たと伝えられています。最初にご案内するのは、そんな紫式部ゆかりの古刹で毎年、旧暦8月15日を含む日程で催される「秋月祭」を愛でる旅です。
-

 『源氏物語』の構想を練るべく紫式部が参籠した石山寺の「月見亭」は、絶好の観月スポット
『源氏物語』の構想を練るべく紫式部が参籠した石山寺の「月見亭」は、絶好の観月スポット
画像提供:一般社団法人石山観光協会
滞在先の「びわ湖大津プリンスホテル」にほど近い港から、貸切船で石山寺へ。船上で奏でられる「よし笛」の音に耳を傾けながら、ふと見上げると澄み切った秋の夜空には、ぽっかり浮かぶ満月が。琵琶湖から流れ出る瀬田川の水面には、月明りが幻想的に揺らめいていることでしょう。
船は20分ほどで瀬田川の西岸に到着。石山寺の境内に足を踏み入れると、そこに広がるのは、行燈でライトアップされた幽玄なる世界です。紫式部が執筆したとされている「源氏の間」が一角に佇む本堂などでは、『源氏物語』に関連した催しが行われ、秋の夜を麗しく彩ります。
なかでも境内の上部にある「月見亭」は、歴代の天皇が訪れ名月を眺めたという絶好の観月スポット。平安時代後期に後白河天皇が石山寺を訪れる際につくられたとされています。紫式部も愛でた中秋の名月をしばし眺めながら、風雅なひと時をお過ごしください。
-
 秋の夜空に浮かぶ満月を愛でながら、貸切船で石山寺へ
秋の夜空に浮かぶ満月を愛でながら、貸切船で石山寺へ
-
 紫式部が物語のインスピレーションを得たという
石山寺の名月 画像提供:一般社団法人石山観光協会
紫式部が物語のインスピレーションを得たという
石山寺の名月 画像提供:一般社団法人石山観光協会
善水寺の葺き替え、近江牛懐石湖国の旅情を心ゆくまで
近江八景の1つとされる「石山の秋月」に酔いしれ、全54帖におよぶ『源氏物語』の壮大なロマンに思いを馳せた翌日は、湖南市の岩根山で、約1300年もの歴史を紡ぐ国宝・善水寺を訪問。50年に1度の檜皮葺(ひわだぶき)屋根の葺き替え作業を見学いただきます。檜の皮を加工した材料を竹釘で打ちとめていく古来の屋根葺き手法を間近にしながら、日本の伝統的な工法と先進技術を体感いただけるでしょう。
湖東の多賀町では、県有数の大社である多賀大社を拝観するとともに、名店「せんなり亭多賀別邸」で、近江牛懐石の昼餐を堪能するグルメなひと時をご用意しました。和牛の三大ブランドならではの細やかな肉質、はんなり甘い脂と芳醇な香りをご満喫ください。
-
 近江牛懐石の昼餐を名店「せんなり亭多賀別邸」で堪能
近江牛懐石の昼餐を名店「せんなり亭多賀別邸」で堪能
-
 50年ぶり、屋根の葺き替え作業がたけなわの国宝・善水寺を訪問
50年ぶり、屋根の葺き替え作業がたけなわの国宝・善水寺を訪問
舟から愛でる名月に浮世を忘れる
京都・大覚寺での夕べ
秋色に染まる京都で平安時代の優雅なるお月見を
時を超え、平安貴族たちと同じ場、同じスタイルで名月を観賞できるとは、なんとロマンに満ちたひと時でしょう。ときめきの舞台は、古都の嵐山に佇む大覚寺です。地元民が親しみを込めて“嵐電(らんでん)”と呼ぶ路面電車を貸切って、四条大宮駅から嵐山駅へと向かう道中も、ほっこり心和みます。
-

 “嵐電”と呼ばれる路面電車で石山寺のある嵐山駅へ
“嵐電”と呼ばれる路面電車で石山寺のある嵐山駅へ
平安時代初期、嵯峨天皇の別邸として建立された大覚寺。その古刹に佇む大沢池は、中国の洞庭湖を模してかたどったと伝えられ、現存する舟遊びの池としては最古のもの。当日は、この池に浮かべた龍頭舟に乗りながら、約1000年前と変わらぬ雅な観月のひと時をお楽しみいただきます。
夜が深まり一般観光客とて姿を消した大覚寺の境内を改めて見回すと、ここが京都の町中かと疑うほど。塀外に建物や電線、町の灯さえも一切見えない静寂の世界に包まれながら小舟に身をゆだねていると、微かに聞こえてくるのは、櫂が立てる水切り音と虫の音ばかり。そして漆黒の夜空には、名にし負う中秋の名月が儚げに輝くとともに、月光を受けて大沢池の水面と諸堂の輪郭が、おぼろげに浮かび上がる幻想美に、思わずため息が出ることでしょう。浮世を忘れるような風流な情景を、たっぷりとご満喫ください。
-

 大覚寺・大沢池に小舟を浮かべ、平安貴族のごとく風流なお月見を
大覚寺・大沢池に小舟を浮かべ、平安貴族のごとく風流なお月見を
-
 大覚寺「庭湖館」の奥の間には、慈雲尊者筆『六大無碍常瑜伽』の軸が
大覚寺「庭湖館」の奥の間には、慈雲尊者筆『六大無碍常瑜伽』の軸が
-
 月を望む場所に祭壇を設け、お団子などを供する「満月法会」
月を望む場所に祭壇を設け、お団子などを供する「満月法会」
運慶渾身の若き日の傑作を円成寺で拝観するひと時も
平安京で雅な観月を堪能したあとは、平城京として栄えたもう1つの古都・奈良へ。柳生街道随一の名刹・円成寺で、運慶作の国宝『大日如来坐像』を拝観していただきます。この仏像は、平安時代から鎌倉時代にかけて写実的で力強い仏像を数多く生み出した、天才仏師・運慶が20代の頃に手がけた傑作。東大寺南大門の『金剛力士像』に連なる、力感ほとばしる気迫を実感していただけることでしょう。
運慶の弾むような若々しさが満ちる仏像をより間近に拝観いただくために、円成寺では8年前に安置するお堂を相應殿へと遷座。凜としてエネルギーに満ちあふれた『大日如来坐像』の表情を、正面のみならず両側面からもじっくりとご覧いただけるようになりました。昼食のひと時は、旧奈良県知事公舎を改修した「紫翠 ラグジュアリーコレクションホテル奈良」で。大正レトロな建築美も趣のあるこのホテルで日本料理をいただきながら、2つの古都での旅の余韻にゆったり浸ってはいかがでしょうか。
-

 運慶が20代の頃に手がけた『大日如来坐像』を円成寺で拝観
運慶が20代の頃に手がけた『大日如来坐像』を円成寺で拝観
風流な日本の秋を心に刻む
出雲の日御碕神社拝殿を貸切り
聖地に舞う神話の世界へ
神々の国・出雲の地で「神在月」の雰囲気に浸る
出雲の地では、「神在月(かみありつき)」と呼ぶ時期に、全国から八百万(やおよろず)の神々がお集まりになるといわれます。3つ目にご案内するのは、そんな神々の国に受け継がれる「出雲神楽」の特別公演を日御碕(ひのみさき)神社で鑑賞。併せて空気も澄んだ早朝に、出雲大社を参拝していただく心洗われる旅です。
-

 「出雲神楽」特別公演の舞台は、日本海に突き出た岬に鎮座する日御碕神社
「出雲神楽」特別公演の舞台は、日本海に突き出た岬に鎮座する日御碕神社
1日目は、羽田空港を発ってお昼時に出雲市に到着。まずは地元素材を活かした日本料理をいただいてから、市内平田町の「木綿街道」を散策しましょう。
その名の通り、かつて木綿の取引で栄えたこの街道は、昔の面影を色濃く残す白壁の土蔵や、妻入り造りの町屋などが並び、そぞろ歩くほどに当時の風情にふれることができます。
日暮れとともに、いよいよ出雲大社から西北約6キロ、日本海に突き出た岬に鎮座する日御碕神社へ。天照大御神(あまてらすおおみかみ)、素盞嗚尊(すさのおのみこと)と、神話に出てくるような神さまが祀られている神社の拝殿で、「出雲神楽」の特別公演をお楽しみください。お囃子とともに繰り広げられる舞は、厳かにして重厚。神々の国で育まれた伝統芸能を堪能するほどに、神秘の世界へと引き込まれていくようです。
-

 勇壮な舞、煌びやかな衣装、ダイナミックなお囃子など、厳かにして重厚な「出雲神楽」
勇壮な舞、煌びやかな衣装、ダイナミックなお囃子など、厳かにして重厚な「出雲神楽」
静やかな出雲大社を朝参り 旬の松葉ガニを満喫するひと時
せっかくの機会ですから、出雲大社での参拝も果たしたいもの。しかしながら催行時は、この大社で「神在祭」が催されることもあり、日中は大混雑が予想されます。
そこで今回、おすすめするのが朝参りです。ホテル・旅館の予約も難しいこの時期に、出雲大社に徒歩圏内の「いにしえの宿 佳雲」に宿泊。6時半に旅館を出発し、人出の少ない早朝の境内を専門ガイドがご案内します。凛と張りつめた空気に包まれながら、数千年の歴史を有する出雲大社の風情に、ゆったりとふれてはいかがでしょうか。
-
 凛と張りつめた空気に包まれながら、人出の少ない出雲大社を朝参り
凛と張りつめた空気に包まれながら、人出の少ない出雲大社を朝参り
-
 滞在先は、出雲大社にも徒歩圏内の「いにしえの宿 佳雲」
滞在先は、出雲大社にも徒歩圏内の「いにしえの宿 佳雲」
山陰の秋の味覚といえば、松葉ガニ。そんな皆さまの想いを満たすのが、米子市の皆生(かいけ)温泉に佇む料亭旅館「やど紫苑亭(しおんてい)」での美食のひと時です。折しも旅の催行時に、松葉ガニの漁が解禁。カニの水揚げ量日本一の境港で揚がったタグ付き松葉ガニの懐石料理をご堪能ください。
-
 「やど紫苑亭」で解禁となったばかりの松葉ガニの懐石料理を
「やど紫苑亭」で解禁となったばかりの松葉ガニの懐石料理を
-
 大山屈指の絶景ポイント・鍵掛峠で晩秋の紅葉観賞に心満ちる
大山屈指の絶景ポイント・鍵掛峠で晩秋の紅葉観賞に心満ちる
日本三大美祭と称される
秋の「高山祭」で、からくりと宵祭を
からくりの妙技に心躍り 宵祭の風情に心満ちる
山並みも町並みも麗しい飛騨高山で開催される、秋祭。それだけで、旅心はときめくことでしょう。ここでご案内するのは京都の「祇園祭」、埼玉の「秩父夜祭」とともに、日本三大美祭の1つに数えられる「高山祭」をお楽しみいただく旅です。
飛騨高山では年に2回お祭りが開催されますが、春の「山王祭」は、上町(旧高山城下町南半分)の氏神様である日枝神社の例大祭。秋の「八幡祭」は、下町(同北半分)の氏神様である櫻山八幡宮の例大祭を指します。多くの観衆で混雑するなか、祭りの会場近くまでジャンボタクシーで移動。彫刻や錺(かざり)金具など、飛騨匠による技が結集された11台の屋台が、江戸時代の面影を残した下町一帯を巡行する様子をご覧いただきます。
なかでも見ものは、布袋台(ほていたい)の屋台で繰り広げられる「からくり奉納」です。2体の唐子が曲芸師のような身のこなしで、次々と棒に飛び移りながら布袋様の肩に乗る妙技と、布袋様が「和光同塵(わこうどうじん)」の文字を描いた旗を揚げるクライマックスに拍手喝采が沸き起こります。
ご希望の皆さまには、日が暮れてから行われる宵祭にもご案内いたします。約100個もの提灯の灯りに浮かび上がる屋台は、昼間とはまた違った優雅さにあふれます。ほかの祭りのような威勢の良いかけ声を発することもなく、笛、太鼓、鉦の音の響きとともにゆったりと巡行していく風情に心洗われることでしょう。
-

 江戸時代の面影を残す下町一帯を11台の屋台が巡行していく
江戸時代の面影を残す下町一帯を11台の屋台が巡行していく
-
 2体の唐子と布袋様の妙技が見ものの「からくり奉納」
2体の唐子と布袋様の妙技が見ものの「からくり奉納」
-
 約100個もの提灯の灯りで屋台が浮かびあがる宵祭
約100個もの提灯の灯りで屋台が浮かびあがる宵祭
秋色に染まる白川郷へ 金沢では「ひがし茶屋街」を
多くの旅人が1度はと想いを馳せる、世界遺産の白川郷にもご案内します。日本の原風景ともいうべき茅葺屋根の合掌造り集落や、田園風景を眺めながらの散策。秋の深まりとともに、錦の山に彩られた白川郷をご満喫ください。旅は飛騨高山、白川郷と白山・加賀温泉郷を結ぶ「白山白川郷ホワイトロード」の山岳ドライブを経て、加賀100万石の城下町・金沢へ。美しい出格子と石畳が続く「ひがし茶屋街」をそぞろ歩くほどに、旅情に満ちた北陸の秋を実感いただけることでしょう。
-
 約1,300年の歴史を刻む山中温泉の名湯でゆったりと
約1,300年の歴史を刻む山中温泉の名湯でゆったりと
-
 宿泊は、名勝・鶴仙渓(かくせんけい)の眺望が麗しい「花紫」で
宿泊は、名勝・鶴仙渓(かくせんけい)の眺望が麗しい「花紫」で
会場近くのホテルに連泊し
湖国の秋を彩る「大津祭」をゆったりと
宵宮の情緒をたっぷりと そして本祭の魅力を観覧席から
日本の秋祭りといえば、「大津祭」も見逃すことができません。「山王祭」、「船幸祭」とともに、湖国三大祭と称されるこの祭りは、782年に創建された天孫神社の祭礼として、約400年続く伝統行事です。
その魅力の1つは、見送り幕や天井画などで飾られた曳山の見事さ。なかには、貴重なゴブラン織りの幕をまとった曳山もあるほどです。そんな装飾やデザインの絢爛さに、かつて港町・宿場町として栄えた大津百町の経済力が偲ばれます。また、「高山祭」の「からくり奉納」とは異なり、13基の曳山それぞれに趣向を凝らしたからくり披露も見どころ。中国の故事にならって鯉が勢い良く龍門滝を登る情景や、商売繁盛の神様・えびす様が鯛を釣りあげる様子を再現したからくり演技に、盛大な拍手が沸きあがります。
そんな「大津祭」の魅力をたっぷりと満喫いただくために、この旅では祭り会場に近く温泉大浴場も備えた、「琵琶湖ホテル」に2連泊。1日目は、提灯を灯した曳山が、心地良く響くお囃子とともに大津の秋の夜を彩る宵宮を見学。2日目は、曳山巡行とともに、からくりの妙技を観覧席からご堪能いただきます。巡行中は、曳山から厄よけのちまきや手拭いが投げられます。運が良ければ、ご利益を授かることができるかも知れません。
-

 湖国三大祭の1つ、約400年続く伝統行事「大津祭」
湖国三大祭の1つ、約400年続く伝統行事「大津祭」
-
 それぞれの曳山が趣向を凝らしたからくりを披露
それぞれの曳山が趣向を凝らしたからくりを披露
-
 見送り幕や天井画などで飾られた曳山の絢爛さに息を呑む
見送り幕や天井画などで飾られた曳山の絢爛さに息を呑む
宇治の銘茶を嗜み 焼物の里・信楽で松茸料理を
例年、定番となっているこの旅の魅力をさらに増すために、今回はルートを変更し初日に京都を訪ねます。まずは、緑茶発祥の地で知られる宇治田原町の「京都きよ泉」で、お茶と銘菓を満喫。焼物の里・信楽町では、約1200年の歴史を刻む信楽焼の窯元「宗陶苑」で伝統の技にふれるとともに、日本料理店「魚仙」では、信楽焼の器で供される旬の松茸料理をお楽しみいただきます。
-
 窯元「宗陶苑」で伝統ある信楽焼の技にふれる
窯元「宗陶苑」で伝統ある信楽焼の技にふれる
-
 信楽焼の器で供される松茸料理を、日本料理店「魚仙」で
信楽焼の器で供される松茸料理を、日本料理店「魚仙」で
“歴史絵巻”のような「時代祭」の行列を
特設観覧席から
華やかにして艶やかな祭りをゆったり、たっぷりと
最後にご案内するのは、平安京遷都1100年を記念して、1895年にはじまった「時代祭」を観覧いただく旅です。葵祭や祇園祭とともに京都三大祭の1つといわれる華やかにして艶やかなこの秋祭りを、特設観覧席でゆったりとお楽しみください。
息を凝らしながら、御池通に設けられた観覧席で座すことしばし。笛・太鼓の音とともに姿を現すのは、「維新勤王隊」の行列です。戊辰戦争時に京都で結成されたこの部隊を先頭に、幕末時から延暦時代まで各時代の衣裳をまとった総勢約2,000名、約2キロにおよぶ行列が次々に目の前を通りゆく様は圧巻です。
それとともに目を見張るのは、衣装や祭具、調度品などの見事さでしょう。それもそのはず、約12,000点におよぶこれらの品々は、時代考証のうえで、京の伝統工芸技術の粋を集めて細部まで忠実に復元されたものばかりなのです。古都の秋空の下で繰り広げられる壮麗な“歴史絵巻”を約2時間、たっぷりとご堪能ください。
-
 平安時代婦人列では、紫式部と清少納言が2人揃って艶やかに ©京都市観光協会
平安時代婦人列では、紫式部と清少納言が2人揃って艶やかに ©京都市観光協会
-
 織田信長が天下統一を目指し上洛した時の様子を再現した、織田公上洛列(おだこうじょうらくれつ)©京都市観光協会
織田信長が天下統一を目指し上洛した時の様子を再現した、織田公上洛列(おだこうじょうらくれつ)©京都市観光協会
古都ならではのひと時に心満ち老舗料理旅館では京懐石を
京都の秋を慈しむ特別なひと時もご用意しました。その1つは、「聖護院(しょうごいん)門跡」の特別公開です。1090年に創建されたこの寺院に伝わる障壁画などから、特別公開される120面余をご覧いただけます。また、秀吉の側室・淀殿が建立し、妹のお江が再建した「養源院」を僧侶の案内とともに特別拝観。異才の絵師・俵屋宗達筆になる『杉戸絵』を鑑賞いただきます。グルメの皆さまには、老舗料理旅館「要庵西富家(かなめあんにしとみや)」で味わう京懐石もとっておきの思い出になるでしょう。
それにしても日本の秋は、なぜにかくも旅心を掻き立てるのでしょうか。しっとりと、旅人を癒すのでしょうか。
-

 「聖護院門跡」では、200面以上伝えられる障壁画のなかから120面余を特別公開
「聖護院門跡」では、200面以上伝えられる障壁画のなかから120面余を特別公開

 『源氏物語』の構想を練るべく紫式部が参籠した石山寺の「月見亭」は、絶好の観月スポット
『源氏物語』の構想を練るべく紫式部が参籠した石山寺の「月見亭」は、絶好の観月スポット 秋の夜空に浮かぶ満月を愛でながら、貸切船で石山寺へ
秋の夜空に浮かぶ満月を愛でながら、貸切船で石山寺へ
 紫式部が物語のインスピレーションを得たという
石山寺の名月 画像提供:一般社団法人石山観光協会
紫式部が物語のインスピレーションを得たという
石山寺の名月 画像提供:一般社団法人石山観光協会
 近江牛懐石の昼餐を名店「せんなり亭多賀別邸」で堪能
近江牛懐石の昼餐を名店「せんなり亭多賀別邸」で堪能
 50年ぶり、屋根の葺き替え作業がたけなわの国宝・善水寺を訪問
50年ぶり、屋根の葺き替え作業がたけなわの国宝・善水寺を訪問

 “嵐電”と呼ばれる路面電車で石山寺のある嵐山駅へ
“嵐電”と呼ばれる路面電車で石山寺のある嵐山駅へ

 大覚寺・大沢池に小舟を浮かべ、平安貴族のごとく風流なお月見を
大覚寺・大沢池に小舟を浮かべ、平安貴族のごとく風流なお月見を
 大覚寺「庭湖館」の奥の間には、慈雲尊者筆『六大無碍常瑜伽』の軸が
大覚寺「庭湖館」の奥の間には、慈雲尊者筆『六大無碍常瑜伽』の軸が
 月を望む場所に祭壇を設け、お団子などを供する「満月法会」
月を望む場所に祭壇を設け、お団子などを供する「満月法会」

 運慶が20代の頃に手がけた『大日如来坐像』を円成寺で拝観
運慶が20代の頃に手がけた『大日如来坐像』を円成寺で拝観





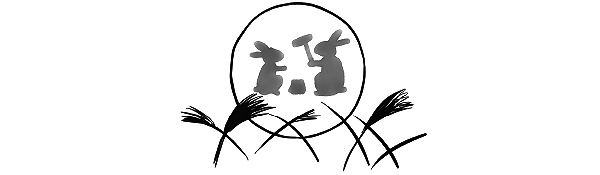







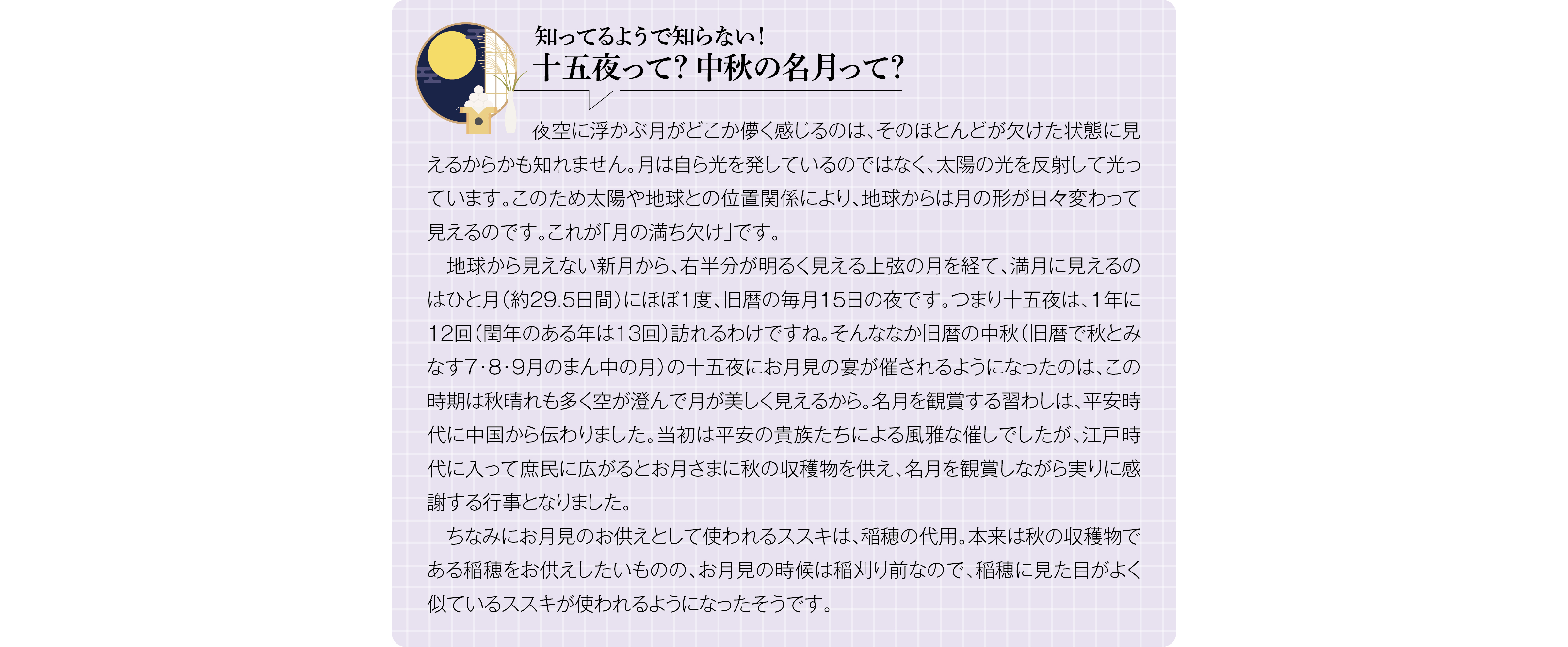
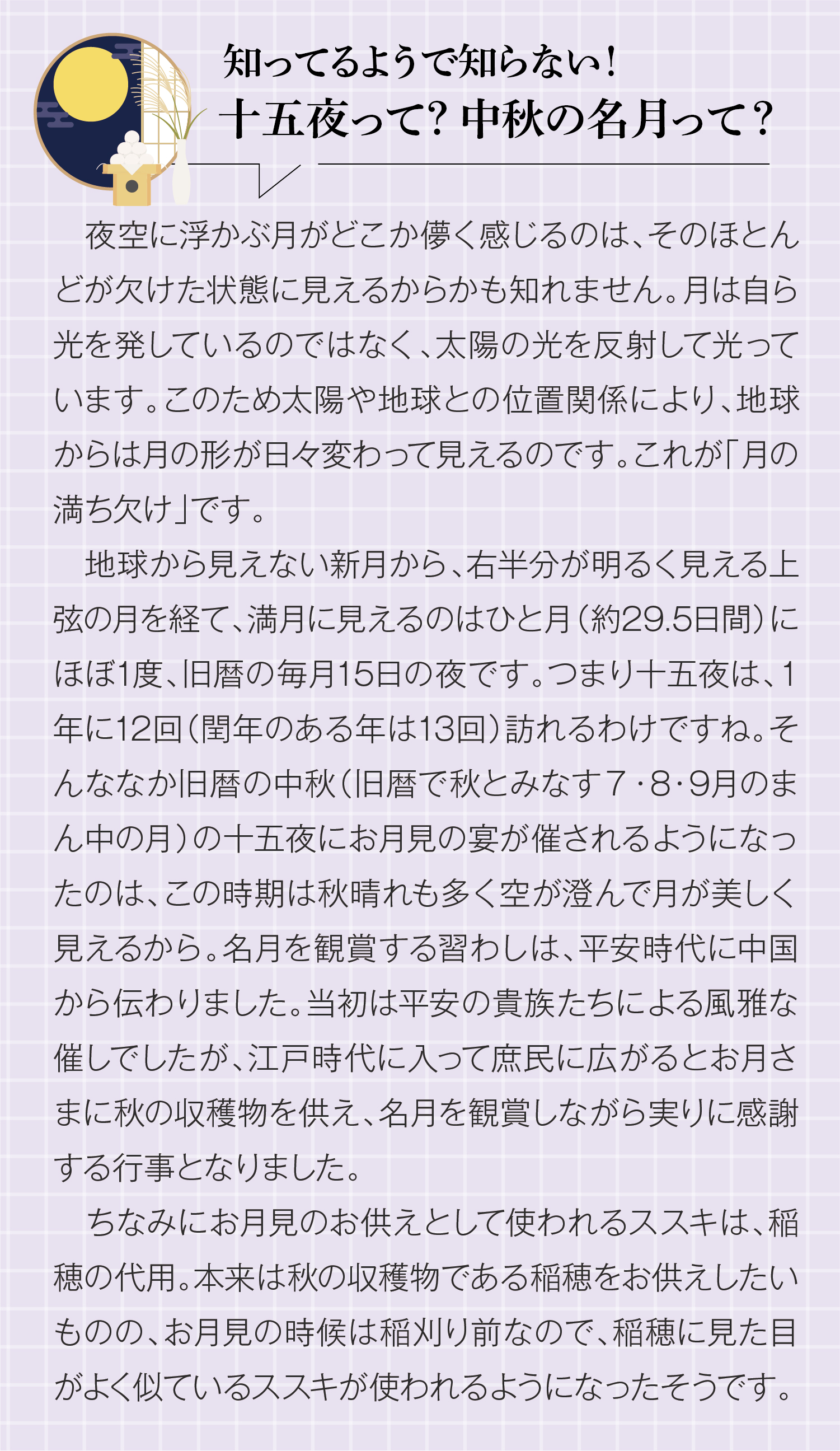






 凛と張りつめた空気に包まれながら、人出の少ない出雲大社を朝参り
凛と張りつめた空気に包まれながら、人出の少ない出雲大社を朝参り
 滞在先は、出雲大社にも徒歩圏内の「いにしえの宿 佳雲」
滞在先は、出雲大社にも徒歩圏内の「いにしえの宿 佳雲」
 「やど紫苑亭」で解禁となったばかりの松葉ガニの懐石料理を
「やど紫苑亭」で解禁となったばかりの松葉ガニの懐石料理を
 大山屈指の絶景ポイント・鍵掛峠で晩秋の紅葉観賞に心満ちる
大山屈指の絶景ポイント・鍵掛峠で晩秋の紅葉観賞に心満ちる




 2体の唐子と布袋様の妙技が見ものの「からくり奉納」
2体の唐子と布袋様の妙技が見ものの「からくり奉納」
 約100個もの提灯の灯りで屋台が浮かびあがる宵祭
約100個もの提灯の灯りで屋台が浮かびあがる宵祭

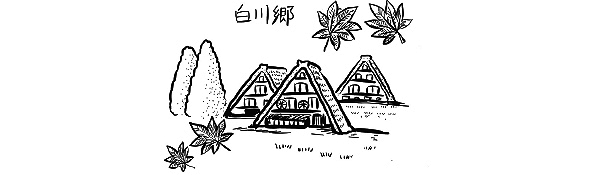
 約1,300年の歴史を刻む山中温泉の名湯でゆったりと
約1,300年の歴史を刻む山中温泉の名湯でゆったりと
 宿泊は、名勝・鶴仙渓(かくせんけい)の眺望が麗しい「花紫」で
宿泊は、名勝・鶴仙渓(かくせんけい)の眺望が麗しい「花紫」で





 それぞれの曳山が趣向を凝らしたからくりを披露
それぞれの曳山が趣向を凝らしたからくりを披露
 見送り幕や天井画などで飾られた曳山の絢爛さに息を呑む
見送り幕や天井画などで飾られた曳山の絢爛さに息を呑む

 窯元「宗陶苑」で伝統ある信楽焼の技にふれる
窯元「宗陶苑」で伝統ある信楽焼の技にふれる
 信楽焼の器で供される松茸料理を、日本料理店「魚仙」で
信楽焼の器で供される松茸料理を、日本料理店「魚仙」で




 平安時代婦人列では、紫式部と清少納言が2人揃って艶やかに ©京都市観光協会
平安時代婦人列では、紫式部と清少納言が2人揃って艶やかに ©京都市観光協会
 織田信長が天下統一を目指し上洛した時の様子を再現した、織田公上洛列(おだこうじょうらくれつ)©京都市観光協会
織田信長が天下統一を目指し上洛した時の様子を再現した、織田公上洛列(おだこうじょうらくれつ)©京都市観光協会




